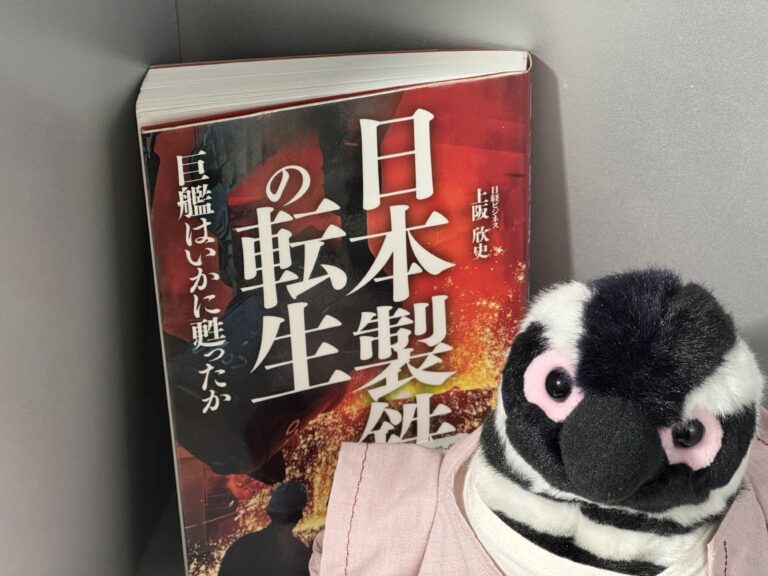小学校の授業で八幡製鉄所が出てきたときに、「この跡地にできたのがスペースワールドです」と習いました(九州だから?)。実際は敷地の遊休地を活用したものですが、製鉄業なんてもう斜陽産業になっているという印象でしたね。30年前の話です。それが今、最先端技術に特化した強い会社に生まれ変わろうとしています。
本書は2020年3月期に赤字転落した日本製鉄が、2019年4月に就任した橋本社長の元でV字回復を遂げていくストーリーです。そのうち赤字事業の解消、自動車業界との値上げ交渉、M&Aについては業界のニュースにもなりました。また環境対策や技術伝承など、長期的なテーマも盛り込まれています。見出しだけを追うと一つ一つは普通の取り組みなのですが、この規模の会社で実際に改革することは難しく、筆者のあとがきではこの実行力こそが王道と評しています。
アメリカで予想される関税引き上げやEUの環境規制など、世界中で保護主義に動きつつあるなか、輸出からローカル生産に切り替えていく流れは必然に感じました。ただ製鉄業のように巨大な設備が必要とされる業界でタイムリーに動くには、やはりトップの実行力がカギとなります。これこそが日本の重厚産業に必要とされる能力なのだと理解しました。
スマホやパソコンで日本のメーカーはさっぱり見なくなりましたが、素材産業はまだまだ健在です。時代の変化に対応しつつ、これからも王道を歩んでもらいたいものです。
本書に登場する環境対応は技術面のみでしたが、実は政治的にも動きがあります。それが元環境事務次官である中井徳太郎の顧問就任です。
この中井氏は、官僚の立場で増税に言及した人物として自由主義界隈では大変嫌われております。とはいえ環境規制は放っておくと厳しくなる一方なので、政治的に対抗するためには甘んじて天下りを受け入れるのも一つの手かと思います。
自分の政治感覚と、製造業に身を置く現実的な立場との狭間で心が引き裂かれそうです。



日本製鉄がUSスチールの買収計画を表明したのが2023年12月、本書が出版されたのが2024年1月です。それから1年で、かなり厳しい状況になってきました。
本書では橋本社長は2024年3月に退くと自ら宣言していたのですが、実際はその後会長に就任していまだにトップに君臨しています。買収関連のニュースでも現橋本会長の発言や写真だけが取り上げられます。本書からは橋本社長ありきの改革のように見えましたので、そこからどのように世代交代を進めていくのが気になるところです。
(2025日2月8日更新)悲観的な見方をしていたら、局面が一気に変わっていました。政治の世界はわからないですね。やはり転生していたのか!